防災の日とは?
2015/09/04
「防災の日」って何?

毎年日本では様々な災害が発生しています。
台風は必ずやってきますし、地震も頻繁に起こります。
他にも津波、噴火、洪水、豪雨、等、様々な災害があります。
そういった自然災害があることを改めて認識し国民の防災意識を高めることを目的として定められているのが「防災の日」です。
国民の防災意識を高めておくとどうなるでしょうか。
・災害に備える(避難グッズの用意等)
・災害が起きた時にとるべき避難行動を知る
こういったことを行う人が増えることが期待されます。
そうなることで少しでも災害の被害が小さくなると良いですね。
「防災の日」の歴史・背景
昭和34年9月26日、伊勢湾台風は潮岬に上陸し全国にわたって大きな被害をもたらしました。
死者・行方不明者は合わせて5000人を超え、その被害規模は戦後最大です。
このことがきっかけとなり、昭和35年に「防災の日」が閣議決定で定められることとなりました。
閣議の結果、「防災の日」は9月1日と定められます。
この9月1日というのは、伊勢湾台風同様、多くの人命を失う悲劇となった関東大震災の発生日である大正12年9月1日に因んでいます。
また、雑節の1つである二百十日は台風の多い厄日とされており、これが太陽暦では9月1日ごろにあたります。
古来から言われていることと日付が一致しているのは興味深いことですね。
「防災の日」はいつ?
「防災の日」は毎年9月1日と定められています。
そして、9月1日を含む1週間は「防災週間」とされています。
「防災の日」には何が行われるの?

「防災の日」には全国各地で消防署、警察、自治体、企業等による防災訓練や行事が行われます。
近くで実施される防災訓練があれば、参加して防災意識を高めておくのも良いかもしれませんね。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
日本は穏やかな気候と自然に恵まれた暮らしやすい国ですので、普段はつい災害のことを忘れてしまいがちです。
ですが、時折厳しい災害が襲ってくる国であることもまた事実です。
地球の構造上、地震が起こりやすく台風が直撃しやすい国であること、それ以外にも様々な災害が起こりうることを普段から頭の片隅にいれて、いざという時のための準備を怠らないようにしておきたいですよね。
過去の悲惨な災害の教訓を活かすために定められた「防災の日」。
この機会に改めて自分の防災対策は大丈夫なのか気にかけてみてはどうでしょうか。

懐中電灯はどこにおいてあるのか?
非常食は準備されているか?
避難経路はどうなっているのか?
そういったちょっとしたチェックが将来自分の命を救うことになるかもしれませんよ。
【関連記事】
台風の対策しっかりしておこう|役立ち情報ナビ
関連記事
-

大曲の花火は花火師日本一決定戦in秋田県大仙市
夏の風物詩、全国高校野球選手権大会。 全国の高校球児が日本一をかけて熱戦を繰り広 …
-

ツール・ド・北海道とは
世の中にはたくさんの自転車レースがあるのですが、そのうちの一つに数えられるものが …
-

目黒のさんま祭りで岩手県宮古産さんま炭火焼を堪能
目黒のさんま祭りはどのようなイベントなのか? 目黒のさんま祭りは、東京都品川区上 …
-

新居浜太鼓祭りとは
新居浜太鼓祭りとは スポンサードリンク 新居浜太鼓祭りは愛媛県の新居浜を代表する …
-

AKB48G成人式の場所は神田明神!2016成人メンバーは?
スポンサーリンク 2016年1月11日は成人式ですね。 新しく成人となった人達の …
-
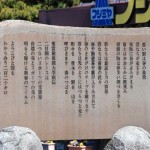
箱根駅伝5区コース変更で歴代山の神は参考記録
スポンサーリンク 箱根駅伝は箱根山をコースにしているため、高低差の激しい駅伝とし …
-

チョコレートの祭典サロン・デュ・ショコラとは
スポンサーリンク バレンタインデーが近くなってくると、チョコレートに興味が湧いて …
-

日本三大花火大会の一つ土浦花火大会とは
日本にはたくさんの花火大会と呼ばれるものがあるのですが、そのうちの一つに土浦花火 …
-

ノーベル賞授賞式日程はいつ?開催場所や中継は?
スポンサーリンク 2015年ノーベル賞は大村智氏の医学生理学賞、梶田隆章氏の物理 …
-

ペルセウス座流星群は今年も極大を楽しもう
星空を眺めていると、宇宙の壮大さを感じてしまいます。 普段の悩みも、宇宙の前には …